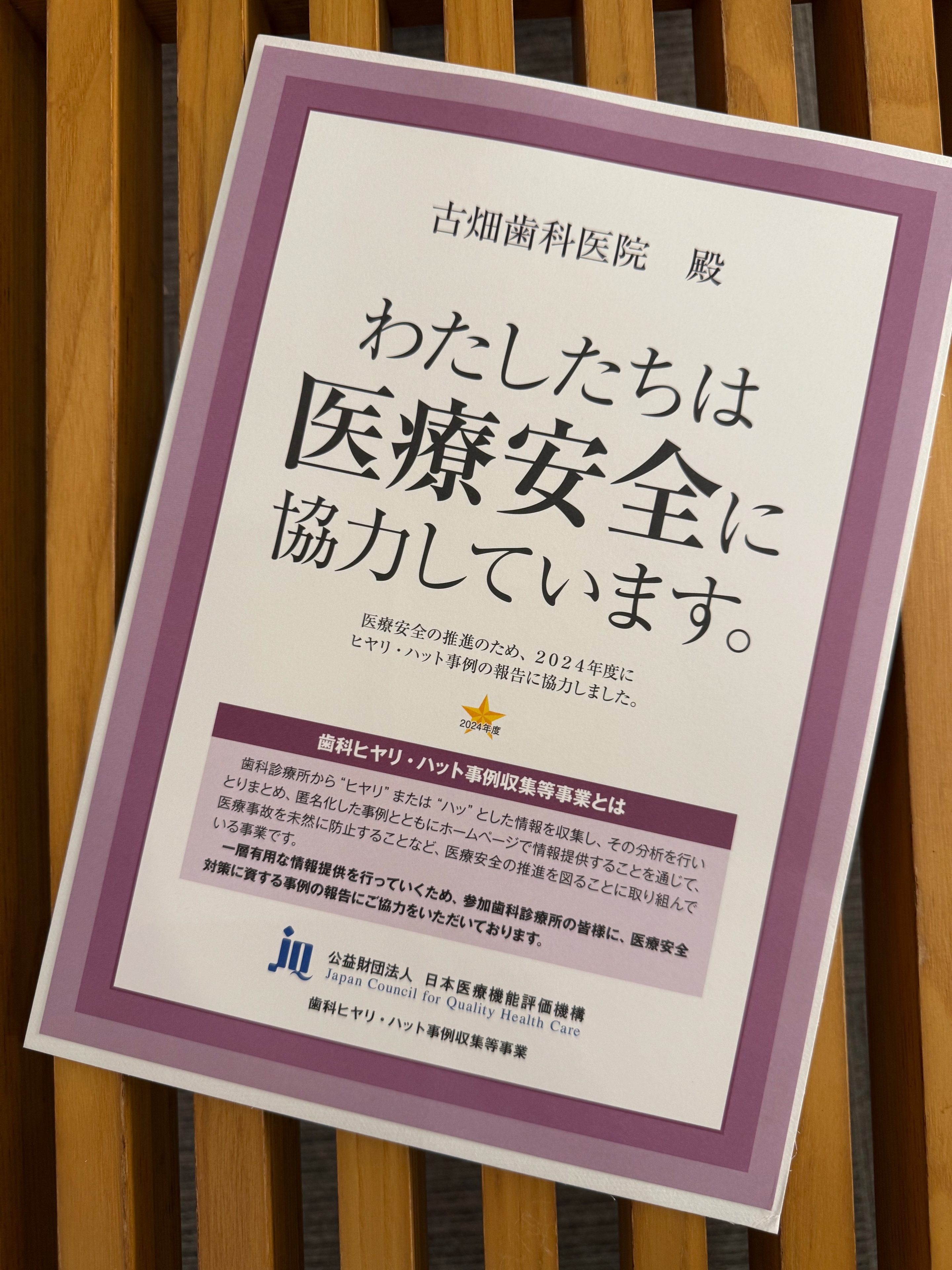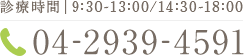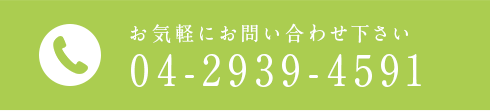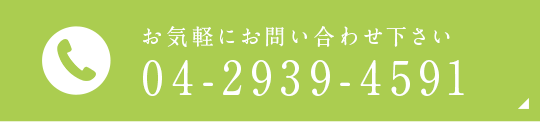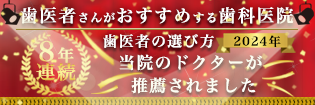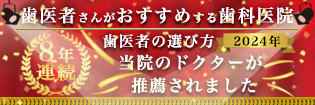院長の古畑です。
2月のレシピカードがの配布が今週から始まっています^^
今月も簡単でとっても美味しい一品です!
今月はビタミンKが豊富で骨粗鬆症の予防に効果がある、香りが良くて彩りにも用いられる「あの食材」を使ったレシピです!
以前もこの食材を使用したレシピをスタッフが作ってくれたことがあります。
あまりこの食材を使う料理をつくる機会がなかったのですが、前回はそのおいしさを再認識させてくれる美味しさでした。
そして今回もめっちゃ美味しい!!簡単に作れるのに、あっという間に食卓から消えてしまうほどの美味しさでした。
副菜として置いておくにはもったいない存在感です。
ぜひメインの一品にしてみてはいかがでしょうか。

写真が上手でなくて、あまり美味しそうに見えませんが・・・めちゃくちゃ美味しいです!
<ビタミンKが骨粗鬆症に有効なメカニズム>
ビタミンKが豊富なレシピですが、なぜ骨粗鬆症予防に有効なのでしょうか。そのメカニズムはいくつか挙げられます。
①オステオカルシンを活性化させる
骨の基質を作るオステオカルシンは、非活性化された状態では骨に結合しにくく、ビタミンKなどの働きで活性化することで骨に結合できるようになります。
その結果、カルシウムと結びつきやすくなることで骨密度の低下を防ぎます。
②骨吸収を抑制する
ビタミンKは骨を吸収する細胞である破骨細胞の働きを抑える働きがあるため、骨の量を維持しやすくさせます。
③ビタミンDとの相互作用
ビタミンDとビタミンKの相互作用で骨へのカルシウムの結合が促されます。
④血管の石灰化を防ぐ
血管内に過剰なカルシウムが石灰化物として沈着することを防ぐことで、血液中のカルシウムを適切に骨に届けることが期待できます。
<ビタミンKを吸収しやすくする工夫>
ビタミンKにはK1とK2の2種類があり、脂溶性ビタミンのため吸収を高める工夫が必要です。
① 脂質と一緒に摂取
ビタミンKは脂溶性なので、脂質と一緒に摂取することで吸収能率を高められます。
例えば・・・
・納豆(ビタミンK2)+卵
・ほうれん草(ビタミンK1)+ナッツ
・ブロッコリー(ビタミンK1)+マヨネーズ
などがは相性が良くておすすめです。
②腸内環境を整える
ビタミンK2は腸内細菌によっても生成されるため、発酵食品(ヨーグルト、味噌、漬物)や食物繊維を積極的に摂取すると良いです。
③ビタミンDとの併用
ビタミンDと一緒に摂ることで、骨へのカルシウムの吸収を高めます。
また日光浴もビタミンDの合成を促進できるため、キャンプできのこ料理!なんていかがでしょう。
④熱に強いが光や酸化に注意
ビタミンKは比較的加熱に強いので調理にはあまり気を使いませんが、光や酸化に弱いので、新鮮なうちに早めに食べるのが理想的と言えます。